スペカズ [カズキ]
彼の名前はカズキ。そう、あのスペース・カズキだ。これまでも宇宙のごく一部の界隈では宇宙一サラッとした奴として知る者は知っていた。それが今や誰もが知るあのスペース・カズキだ。
スペース・カズキの名前が知れ渡った最初の理由は彼が宇宙の中心を発見した事にある。
あんなのは宇宙の中心なんかじゃあ無い。とか、色色と難癖をつける輩はどこにでもいるものだが、本物かどうかの判定は惑星丸ごとをAI化させた惑星AIその三種に委ねられている。一種でも0%の判定を下せば問答無用で却下される。仮に二種が50%以上の判定を下したとしても残りの一種が0%なら即刻却下。
カズキの場合は特殊で三種ともが1%の判定を下した。
これをどうとるかでいまだ論議は続いている。宇宙の中心(仮)にするという案も出ているようだがどうなる事だろう。
「いやぁでもしかしビックリしたなあ。宇宙の中心に辿り着くと宇宙の裏側に行けるとは思わなかったよ。んで裏の裏が表じゃないって所に超マジビビったし。行けば行くほどどんどん裏に裏に行ってもう二度と戻れないんじゃないかと思って宇宙の裏側でわんわん泣いちゃった。
真っ暗闇の中で泣き疲れ果てた時に白い光が見えてそこに向かったら戻れたんだけど不思議な体験だったなあ。
今でも本当に元に戻れたのか確信は無いんだけどさ。」
とは彼が初対面の私にフランクに語ってくれたエピソードの一つだ。
宇宙の中心の発見者。それが彼の名前が宇宙に知れ渡ったきっかけではある。それをさらに全宇宙規模まで拡大させたのは彼の名前を冠した学園ドラマ『3年μ組スペカズ先生』の放送が決定的だった。
主人公の名前がスペカズ・サ=カモトであるという事だけではあるが、ドラマ内で度々主人公がカズキの事をリスペクトした事によって全宇宙のじいちゃんばあちゃん父さん母さん坊ちゃんお嬢ちゃんに幅広く知れ渡った。
なによりもドラマの内容が素晴らしかった。特に第2シーズンの多元宇宙における第3次受験戦争とそれによって引き起こされた学校内暴力がスペース・サクラ中学にも及ぶ中で、暴力を生んだ原因は社会からの偏見や差別が根底にあると訴えるスペカズ先生の姿に全視聴者が涙したと言われている。
スペカズ先生の口癖「そげん言ってもしょんなかけん」はその年の宇宙流行語大賞に選ばれた事は皆さんもご存知の事だろう。
この度待望のスペカズ先生劇場版の製作が決まり驚くことにその主役はカズキが演じるという。
その事でテレビドラマ版の主役キム・タク氏との不仲説も浮上したが、根も葉もない噂話に過ぎないとカズキは完全否定し、タク氏は沈黙を貫いている。
演技経験ゼロのカズキにスペカズ先生を演じきれるのか?それは誰もが不安に思う事だろう。しかし私は言いたい。不安など何一つ無いのだと。カズキの演じるスペカズ先生に大いに期待しよう。
彼のスペース探偵時代からのモットー、依頼された仕事は完璧にやり遂げる。はもうすでに実証されているではないか。
彼は宇宙の中心の発見者スペース・カズキなのだ。
スペース・カズキの名前が知れ渡った最初の理由は彼が宇宙の中心を発見した事にある。
あんなのは宇宙の中心なんかじゃあ無い。とか、色色と難癖をつける輩はどこにでもいるものだが、本物かどうかの判定は惑星丸ごとをAI化させた惑星AIその三種に委ねられている。一種でも0%の判定を下せば問答無用で却下される。仮に二種が50%以上の判定を下したとしても残りの一種が0%なら即刻却下。
カズキの場合は特殊で三種ともが1%の判定を下した。
これをどうとるかでいまだ論議は続いている。宇宙の中心(仮)にするという案も出ているようだがどうなる事だろう。
「いやぁでもしかしビックリしたなあ。宇宙の中心に辿り着くと宇宙の裏側に行けるとは思わなかったよ。んで裏の裏が表じゃないって所に超マジビビったし。行けば行くほどどんどん裏に裏に行ってもう二度と戻れないんじゃないかと思って宇宙の裏側でわんわん泣いちゃった。
真っ暗闇の中で泣き疲れ果てた時に白い光が見えてそこに向かったら戻れたんだけど不思議な体験だったなあ。
今でも本当に元に戻れたのか確信は無いんだけどさ。」
とは彼が初対面の私にフランクに語ってくれたエピソードの一つだ。
宇宙の中心の発見者。それが彼の名前が宇宙に知れ渡ったきっかけではある。それをさらに全宇宙規模まで拡大させたのは彼の名前を冠した学園ドラマ『3年μ組スペカズ先生』の放送が決定的だった。
主人公の名前がスペカズ・サ=カモトであるという事だけではあるが、ドラマ内で度々主人公がカズキの事をリスペクトした事によって全宇宙のじいちゃんばあちゃん父さん母さん坊ちゃんお嬢ちゃんに幅広く知れ渡った。
なによりもドラマの内容が素晴らしかった。特に第2シーズンの多元宇宙における第3次受験戦争とそれによって引き起こされた学校内暴力がスペース・サクラ中学にも及ぶ中で、暴力を生んだ原因は社会からの偏見や差別が根底にあると訴えるスペカズ先生の姿に全視聴者が涙したと言われている。
スペカズ先生の口癖「そげん言ってもしょんなかけん」はその年の宇宙流行語大賞に選ばれた事は皆さんもご存知の事だろう。
この度待望のスペカズ先生劇場版の製作が決まり驚くことにその主役はカズキが演じるという。
その事でテレビドラマ版の主役キム・タク氏との不仲説も浮上したが、根も葉もない噂話に過ぎないとカズキは完全否定し、タク氏は沈黙を貫いている。
演技経験ゼロのカズキにスペカズ先生を演じきれるのか?それは誰もが不安に思う事だろう。しかし私は言いたい。不安など何一つ無いのだと。カズキの演じるスペカズ先生に大いに期待しよう。
彼のスペース探偵時代からのモットー、依頼された仕事は完璧にやり遂げる。はもうすでに実証されているではないか。
彼は宇宙の中心の発見者スペース・カズキなのだ。
2017-12-22 20:04
コメント(0)
宇宙の中心のカズキ [カズキ]
宇宙において人間とはちっぽけな取るに足らない存在である。その事に宇宙に進出して人間は気付いた。いや宇宙に進出する以前から気付いてはいた。その事に気付かぬふりをしていたのだ。
しかし実際に宇宙を目の当たりにしてその事に気付かぬふりをし続ける事は困難だった。
人類という生き物が地球という星に誕生してからわずか数千年。それ以前に地球という星が誕生してから何十億年という月日、地球は太陽の周囲を回り続け、その太陽系もまた銀河系の周囲を回り続け、その銀河系もまた何かの周囲を回り続けていた。
黄金のスペースシップ、ゴールデン・ベアー号の搭乗員は人類で初めて太陽系を離れようとしていた。
搭乗員であるカズキたちが目指しているのは宇宙の中心である。
何も好き好んで目指しているわけではない。スペース探偵であるカズキに依頼があったからだ。
少し時間を遡る事にしよう。
「スペース探偵カズキ。カズキ=フランシス・ド・エナリ3世よ。」
カズキが他人からフルネームで呼ばれる事は滅多にない。またカズキもフルネームで呼ばれる事を好ましく思っていなかった。
「そなたへのこの依頼承知してくれる事をわたくしは望んでいる。カズキ=フランシス・ド・エナリ3世よ。」
この大仰な言い回しをする依頼主は誰あろうゴールデン・ベアー号の本来の持ち主である王様だった。
断れるはずもなかった。ゴールデン・ベアー号を頂いてきたのにはそれなりの理由は有ったが、それを犯罪と言われれば返す言葉は無かった。
なにより今現在ゴールデン・ベアー号は王立宇宙軍第3艦隊所属の大型戦闘スペースシップ数十隻に包囲されている。この有無を言わさぬ状況下でこちらに選択肢を与えて下さりやがる王家の気品とやらにカズキは苛立ちを隠せなかった。
「ちっ・・・、オーケイ分かった。引き受けるぜその依頼。」
宇宙の中心はどこにあるのか?
それは大宇宙時代を迎えた人類にとっても未だ解けない謎だ。その謎は人類には永遠に解き明かされないであろう。というのがその答えとしてもはや定説となっていた。
しかしその謎を解くカギを人類は手に入れた。
そのカギはゴールデン・ベアー号にあった。ゴールデン・ベアー号が王家の至宝と呼ばれる理由は何もその黄金の機体だけにあったわけではなかった。
その理由はゴールデン・ベアー号に搭載されていた人工知能のキョウコにあった。
キョウコを開発したチームがその完成を祝い戯れに「宇宙の中心は」と音声入力したところ、即座にキョウコは宇宙の中心の座標をモニターに表示したのだ。
続く・・・
いや続かない。
しかし実際に宇宙を目の当たりにしてその事に気付かぬふりをし続ける事は困難だった。
人類という生き物が地球という星に誕生してからわずか数千年。それ以前に地球という星が誕生してから何十億年という月日、地球は太陽の周囲を回り続け、その太陽系もまた銀河系の周囲を回り続け、その銀河系もまた何かの周囲を回り続けていた。
黄金のスペースシップ、ゴールデン・ベアー号の搭乗員は人類で初めて太陽系を離れようとしていた。
搭乗員であるカズキたちが目指しているのは宇宙の中心である。
何も好き好んで目指しているわけではない。スペース探偵であるカズキに依頼があったからだ。
少し時間を遡る事にしよう。
「スペース探偵カズキ。カズキ=フランシス・ド・エナリ3世よ。」
カズキが他人からフルネームで呼ばれる事は滅多にない。またカズキもフルネームで呼ばれる事を好ましく思っていなかった。
「そなたへのこの依頼承知してくれる事をわたくしは望んでいる。カズキ=フランシス・ド・エナリ3世よ。」
この大仰な言い回しをする依頼主は誰あろうゴールデン・ベアー号の本来の持ち主である王様だった。
断れるはずもなかった。ゴールデン・ベアー号を頂いてきたのにはそれなりの理由は有ったが、それを犯罪と言われれば返す言葉は無かった。
なにより今現在ゴールデン・ベアー号は王立宇宙軍第3艦隊所属の大型戦闘スペースシップ数十隻に包囲されている。この有無を言わさぬ状況下でこちらに選択肢を与えて下さりやがる王家の気品とやらにカズキは苛立ちを隠せなかった。
「ちっ・・・、オーケイ分かった。引き受けるぜその依頼。」
宇宙の中心はどこにあるのか?
それは大宇宙時代を迎えた人類にとっても未だ解けない謎だ。その謎は人類には永遠に解き明かされないであろう。というのがその答えとしてもはや定説となっていた。
しかしその謎を解くカギを人類は手に入れた。
そのカギはゴールデン・ベアー号にあった。ゴールデン・ベアー号が王家の至宝と呼ばれる理由は何もその黄金の機体だけにあったわけではなかった。
その理由はゴールデン・ベアー号に搭載されていた人工知能のキョウコにあった。
キョウコを開発したチームがその完成を祝い戯れに「宇宙の中心は」と音声入力したところ、即座にキョウコは宇宙の中心の座標をモニターに表示したのだ。
続く・・・
いや続かない。
スペース・ジコショーカイ [カズキ]
「俺の名前はカズキ。 カズキ・エナリ。
スペース探偵をやっている。
黄金のスペースシップ、ゴールデン・ベアー号のキャプテンでもある。
相棒のみよ子はゴールデン・ベアー号のパイロット。かなり頼りになる奴だ。ヤ・クーザとかいう団体が使う言葉をヒ・ロッシマの方言で喋るのが好きな角刈りの似合う女の子さ。
俺たちのゴールデン・ベアー号はちょいと訳有りでね。なあに、それほど物騒な話じゃないんだが。
この宇宙時代においても探偵ってのは浮気調査が主な仕事なんだ。あの時はある惑星の王様の浮気調査を王様の第三夫人に依頼されたんだが、一夫多妻制でなんで浮気?と一瞬疑問に思ったものの、依頼された仕事は完璧にこなすのが俺の主義でね。
王様は確かに浮気をしていた。その証拠は俺のスペースカメラがばっちり捉えスペースフィルムにしっかりと焼き付けた。
ただ、それがバレると王様はその浮気相手を第二十五夫人にしちまったんだ。それにはいささか拍子抜けしたが、それで第三夫人が納得したのには驚いたな。
で、いざ報酬を受け取るって段になって第三夫人が言うんだが、『わたくしは浮気調査を依頼したがこの度この件は浮気では無くなった・・・。』
ってそれっきり俺を見たまま黙り込んだんだ。このだんまりが何を意味しているのかを理解するのには、時に空気を読み過ぎると言われる俺でも手間取っちまった。
静まり返った大広間のソファーに向かい合い黙って座る俺と第三夫人。その静寂は永遠に続くんじゃないかと思ったよ。
春のうららかな日差しがレースのカーテン越しにキラキラと輝いていてさ。ああ、もうすぐスペース・ゴールデンウィークだなあ、それが終わったらスペース梅雨前線が北上してきてまた蒸し蒸しするなあ、でもそれが過ぎればスペース夏休みがやって来るなあ、今年のスペース夏休みには新しいとびっきりサラッとしたスペース海水パンツを買ってスペース海水浴にでも行こうかなあ・・・
なんて現実逃避してたんだが、無言のまま鬼の形相で俺を睨んでいる第三夫人に気付いてこのだんまりについての意味を真剣に考える事にしたんだ。
・・・あ、この御夫人値切ろうとしてんな。
と不意に気付いたよ。
しかし、さすがにその屁理屈は無えなあと思ったんだが、気が付いたら俺の後ろにロボット兵がずらりと並んでいて有無を言わさずその部屋から連れ出されちまった。
で、結局値切るどころか踏み倒されたんだが、そこでその王家の至宝と言われる黄金のスペースシップ、ゴールデン・ベアー号を報酬の代わりに頂いてきたってわけさ。
まあそっからが大変で、ゴールデン・ベアー号を取り戻そうとする王家の軍隊やら至宝を横取りしようとするスペース盗賊たちに追われたりで・・・うわあああっ!」
突如爆発音とともに激しい振動がゴールデン・ベアー号を襲った。
「なんじゃあっ!尾翼をいかれよった!訳分からん船がどえらいスピードで突っ込んできよるわいっ!」みよ子が状況を報告した。
ミサイルやらビーム砲の攻撃を盛大に仕掛けてくる正体不明のスペースシップ。
「どーするんじゃあっ!!」
「決まってんだろっ!やられたらやり返すっ!みよ子、エンジン出力全開っ!」ミサイルレバーを握る声は何故か弾んでいた。
彼の名前はカズキ。 カズキ=フランシス・ド・エナリ3世。人呼んでスペース探偵カズキだ。
スペース探偵をやっている。
黄金のスペースシップ、ゴールデン・ベアー号のキャプテンでもある。
相棒のみよ子はゴールデン・ベアー号のパイロット。かなり頼りになる奴だ。ヤ・クーザとかいう団体が使う言葉をヒ・ロッシマの方言で喋るのが好きな角刈りの似合う女の子さ。
俺たちのゴールデン・ベアー号はちょいと訳有りでね。なあに、それほど物騒な話じゃないんだが。
この宇宙時代においても探偵ってのは浮気調査が主な仕事なんだ。あの時はある惑星の王様の浮気調査を王様の第三夫人に依頼されたんだが、一夫多妻制でなんで浮気?と一瞬疑問に思ったものの、依頼された仕事は完璧にこなすのが俺の主義でね。
王様は確かに浮気をしていた。その証拠は俺のスペースカメラがばっちり捉えスペースフィルムにしっかりと焼き付けた。
ただ、それがバレると王様はその浮気相手を第二十五夫人にしちまったんだ。それにはいささか拍子抜けしたが、それで第三夫人が納得したのには驚いたな。
で、いざ報酬を受け取るって段になって第三夫人が言うんだが、『わたくしは浮気調査を依頼したがこの度この件は浮気では無くなった・・・。』
ってそれっきり俺を見たまま黙り込んだんだ。このだんまりが何を意味しているのかを理解するのには、時に空気を読み過ぎると言われる俺でも手間取っちまった。
静まり返った大広間のソファーに向かい合い黙って座る俺と第三夫人。その静寂は永遠に続くんじゃないかと思ったよ。
春のうららかな日差しがレースのカーテン越しにキラキラと輝いていてさ。ああ、もうすぐスペース・ゴールデンウィークだなあ、それが終わったらスペース梅雨前線が北上してきてまた蒸し蒸しするなあ、でもそれが過ぎればスペース夏休みがやって来るなあ、今年のスペース夏休みには新しいとびっきりサラッとしたスペース海水パンツを買ってスペース海水浴にでも行こうかなあ・・・
なんて現実逃避してたんだが、無言のまま鬼の形相で俺を睨んでいる第三夫人に気付いてこのだんまりについての意味を真剣に考える事にしたんだ。
・・・あ、この御夫人値切ろうとしてんな。
と不意に気付いたよ。
しかし、さすがにその屁理屈は無えなあと思ったんだが、気が付いたら俺の後ろにロボット兵がずらりと並んでいて有無を言わさずその部屋から連れ出されちまった。
で、結局値切るどころか踏み倒されたんだが、そこでその王家の至宝と言われる黄金のスペースシップ、ゴールデン・ベアー号を報酬の代わりに頂いてきたってわけさ。
まあそっからが大変で、ゴールデン・ベアー号を取り戻そうとする王家の軍隊やら至宝を横取りしようとするスペース盗賊たちに追われたりで・・・うわあああっ!」
突如爆発音とともに激しい振動がゴールデン・ベアー号を襲った。
「なんじゃあっ!尾翼をいかれよった!訳分からん船がどえらいスピードで突っ込んできよるわいっ!」みよ子が状況を報告した。
ミサイルやらビーム砲の攻撃を盛大に仕掛けてくる正体不明のスペースシップ。
「どーするんじゃあっ!!」
「決まってんだろっ!やられたらやり返すっ!みよ子、エンジン出力全開っ!」ミサイルレバーを握る声は何故か弾んでいた。
彼の名前はカズキ。 カズキ=フランシス・ド・エナリ3世。人呼んでスペース探偵カズキだ。
スペース・ナンバーワン・カズキ [カズキ]
カズキのそれはサラッとしていた。
他の者のはゴワゴワしていた。
スペースジャケットの事だ。
サラッとしているカズキのスペースジャケットは特注のあつらえ物だった。
何も初めからあつらえていたわけではなかった。当初は他の者と同様に既製品を着用していたがそのゴワゴワ感にどうしても馴染めなかった。
ミサイルレバーを握る時にも対戦車用バズーカーを構える時にもいつでもゴワゴワするあの感覚に苛苛していた。
遂には業者に無理を言ってカズキ・スペシャルのスペースジャケットをあつらえる事となった。
スペースジャケットに求められるのは何よりも安全性である。繊維にはダイアモンドの粉末が織り込まれ、硬化カーボンのワイヤーがジャケット内に張り巡らされていた。
安全を得るためにゴワゴワ感は致し方ない所であり、誰しもが納得していた事だった。
そこにカズキは一石を投じた。
ダイアモンドの粉末ではなく中国産の最高級の絹を織り込み、ワイヤーはすべて取っ払った。
それが「カズキのスペースジャケットはゴワゴワではなくサラッとしているねぇ」と人々に言われる由縁である。
最高級の絹を使用しているだけあって光沢もしっとりと煌めいており、それもカズキのお気に入りだった。
しかし、それが故にカズキのスペースジャケットの安全性は既製品と較べ40%ほど劣る事となる。
宇宙での40%は限りなく大きいものだ。全ての事においてわずか0.01%の誤差が生死を分ける。人間にとって宇宙とはそれほど過酷な場所である。
それでもカズキは40%の安全性と引き換えに爽やかな着心地を選んだ。
安全性を捨てたからにはデザインにもこだわった。スペースジャケットには不必要な襟をつけボタンも付けた。カラーリングは前腕部分だけを色違いにした。そして左胸にワンポイントの黄金の熊のデザインをあしらった。
それは見るからにポロシャツのデザインだった。
カズキはそのポロシャツのように見えるスペースジャケットの中に本当のポロシャツを着ていた。
それを見たみよ子は「ポロシャツ・オン・ポロシャツやねえ」と呆れて言った。
カズキは事あるごとにそのカズキ・スペシャルのスペースジャケットを自慢した。
それが顕著に表れるのが仕事明けに訪れる各スペースステーション内のスペーススナックにおいてである。
店内に入るととりあえず真っ先に自慢のスペースジャケットを脱ぐ。脱ぐ必要の無い場合であってもとりあえず脱ぐ。
そして脱いだスペースジャケットを目ざとく見つけていた若いスペースホステスに渡すのであった。
若いスペースホステスの反応はそれは素直なものである。その軽さに驚き、サラッとした手触りに感嘆し、しっとりとした光沢に溜息を漏らすのであった。
「お嬢さん、それは中国の養蚕農家の方が丹精込めて作り上げた最高級の絹を使用しているからなんですよ」
カズキの自慢はいつもそのようにして始まるのだった。
その後に店内で延々と続く
「さあ持ってごらん」
「さあ触れてごらん」
「さあ見てごらん」
といったやり取りはもはやルーチンと化ししていた。
今宵もまたこの限りなく広大な宇宙のどこかのスペースステーションのスペーススナックでスペースホステスを相手にそのルーチンなやり取りは繰り返されているだろう。
何故ならカズキのそれは宇宙で一番サラッとしているのだから。
他の者のはゴワゴワしていた。
スペースジャケットの事だ。
サラッとしているカズキのスペースジャケットは特注のあつらえ物だった。
何も初めからあつらえていたわけではなかった。当初は他の者と同様に既製品を着用していたがそのゴワゴワ感にどうしても馴染めなかった。
ミサイルレバーを握る時にも対戦車用バズーカーを構える時にもいつでもゴワゴワするあの感覚に苛苛していた。
遂には業者に無理を言ってカズキ・スペシャルのスペースジャケットをあつらえる事となった。
スペースジャケットに求められるのは何よりも安全性である。繊維にはダイアモンドの粉末が織り込まれ、硬化カーボンのワイヤーがジャケット内に張り巡らされていた。
安全を得るためにゴワゴワ感は致し方ない所であり、誰しもが納得していた事だった。
そこにカズキは一石を投じた。
ダイアモンドの粉末ではなく中国産の最高級の絹を織り込み、ワイヤーはすべて取っ払った。
それが「カズキのスペースジャケットはゴワゴワではなくサラッとしているねぇ」と人々に言われる由縁である。
最高級の絹を使用しているだけあって光沢もしっとりと煌めいており、それもカズキのお気に入りだった。
しかし、それが故にカズキのスペースジャケットの安全性は既製品と較べ40%ほど劣る事となる。
宇宙での40%は限りなく大きいものだ。全ての事においてわずか0.01%の誤差が生死を分ける。人間にとって宇宙とはそれほど過酷な場所である。
それでもカズキは40%の安全性と引き換えに爽やかな着心地を選んだ。
安全性を捨てたからにはデザインにもこだわった。スペースジャケットには不必要な襟をつけボタンも付けた。カラーリングは前腕部分だけを色違いにした。そして左胸にワンポイントの黄金の熊のデザインをあしらった。
それは見るからにポロシャツのデザインだった。
カズキはそのポロシャツのように見えるスペースジャケットの中に本当のポロシャツを着ていた。
それを見たみよ子は「ポロシャツ・オン・ポロシャツやねえ」と呆れて言った。
カズキは事あるごとにそのカズキ・スペシャルのスペースジャケットを自慢した。
それが顕著に表れるのが仕事明けに訪れる各スペースステーション内のスペーススナックにおいてである。
店内に入るととりあえず真っ先に自慢のスペースジャケットを脱ぐ。脱ぐ必要の無い場合であってもとりあえず脱ぐ。
そして脱いだスペースジャケットを目ざとく見つけていた若いスペースホステスに渡すのであった。
若いスペースホステスの反応はそれは素直なものである。その軽さに驚き、サラッとした手触りに感嘆し、しっとりとした光沢に溜息を漏らすのであった。
「お嬢さん、それは中国の養蚕農家の方が丹精込めて作り上げた最高級の絹を使用しているからなんですよ」
カズキの自慢はいつもそのようにして始まるのだった。
その後に店内で延々と続く
「さあ持ってごらん」
「さあ触れてごらん」
「さあ見てごらん」
といったやり取りはもはやルーチンと化ししていた。
今宵もまたこの限りなく広大な宇宙のどこかのスペースステーションのスペーススナックでスペースホステスを相手にそのルーチンなやり取りは繰り返されているだろう。
何故ならカズキのそれは宇宙で一番サラッとしているのだから。
スペース・カズキ [カズキ]
「ちっ」
カズキの表情に焦りが見えてきた。
出力180%で航行しているのにも拘らず正体不明のスペースシップを一向に引き離せないでいた。
「ええい、出力を200%に上げろっ!」カズキは操縦席にいるパイロットに向かって怒鳴った。
「そりゃあ無茶じゃけえっ!」パイロットは簡潔に答えを出した。
そうこのスペースシップ、ゴールデン・ベアー号のパイロットでありカズキの長年の相棒であるみよ子の答えはいつでも簡潔でありそして正しかった。
今現在においてもこの出力のままで航行していればいずれ原子炉エンジンに支障をきたす事は誰が見ても明らかだ。
船内がガタガタと大きく振動していた。船内温度も急激に上昇していた。
「ちっ」。カズキは拳を強く握りしめウィンドウスクリーンに映るスペースシップを睨みみよ子に告げた。
「出力を120%にダウン」
正体不明のスペースシップはゴールデン・ベアー号との距離をみるみる間に詰めてきた。
しかし射程距離に入ってもミサイルもビーム砲も撃ってはこなかった。恐らく弾切れなのだろう。あれだけ盛大な攻撃を仕掛けたのならば当然の事ではある。
それはこちらにも言えた事だ。ゴールデン・ベアー号も弾切れだった。盛大な攻撃を仕掛けられたならば盛大にやり返す。それがカズキの流儀だ。
今回はどちらの攻撃も相手に致命傷を与えるには至らなかった。しかし不意打ちを喰らった分のゴールデン・ベアー号の損害は大きかった。それが正体不明のスペースシップを振り切れなかった理由でもある。
一撃必中の攻撃が失敗したにも拘らず尚も追跡を止めようとしないスペースシップの意図する所は何なのか。
カズキは理解していた。
それはみよ子も同じだった。「こりゃあ本気で体当たりする気じゃ」
「・・・ああ」カズキは静かに頷いた。
「出力を80%にダウン」カズキはみよ子に告げた。
「なんじゃとぉっ!?」みよ子は驚いた。後8,000kmほどでアステロイドベルトの存在が確認されていた。そこに逃げ込めばスペースシップを振り切ることが出来る。カズキはそれを目指すものだと思っていた。
みよ子はカズキの顔を覗き込んだ。
カズキの表情には先ほどの焦りの色は見えなかった。落ち着いている。むしろ微かに笑っているようにも思えた。
この表情の時のカズキは信頼に値する。みよ子はそう思っていた。確かにアステロイドベルトまでは遠過ぎた。
「出力80%」みよ子は従った。
スペースシップがあっという間に間合いを詰める。その距離100km。
60・・・
40・・・
20・・・
「1号エンジンをパージする!」カズキの声が静まり返った船内に響いた。
「なっ、なん・・・」みよ子が驚く前にカズキが強化プラスチックカバーを叩き割り、中にある赤いレバーを力強く引いた。
稼働中のエンジンをパージする事など前代未聞である。パージした瞬間に爆発を起こしてもなんの不思議もない。
出力を低下させたことによって一時的に冷却された1号エンジンは爆発することなく射出された。それに伴いゴールデン・ベアー号のスピードも急激に落ちた。
「みよ子、出力全開!急げっ!」
「なっ、なんじゃあっ!!」みよ子は残りのエンジンを全開にした。
猛スピードで突っ込んできたスペースシップにこの近距離で突如現れた障害物を避ける事は不可能だった。スペースシップの鼻面にゴールデン・ベアー号の1号エンジンがのめり込む。
船内を粉々に破壊しながら尚も1号エンジンは止まる気配すらなかった。それはあたかもスペースシップのエンジンルームを目指しているがごとく破壊の限りを尽くして突き進む。
暫くの間、宇宙にはいつもの静寂が訪れていた。しかし船体内部から幾条もの光線をほとばしらせた後大爆発を起こしたスペースシップがその静寂を打ち消す。
爆発はゴールデン・ベアー号も巻き込んだが、残り2基のエンジンを250%の出力でその場を緊急離脱し被害を最小限にとどめた。
爆発のまばゆい明かりはとても美しかった。そしてその明かりを全身に受けた黄金の機体ゴールデン・ベアー号は漆黒の宇宙の暗闇の中一際光り輝いていた。
カズキの表情に焦りが見えてきた。
出力180%で航行しているのにも拘らず正体不明のスペースシップを一向に引き離せないでいた。
「ええい、出力を200%に上げろっ!」カズキは操縦席にいるパイロットに向かって怒鳴った。
「そりゃあ無茶じゃけえっ!」パイロットは簡潔に答えを出した。
そうこのスペースシップ、ゴールデン・ベアー号のパイロットでありカズキの長年の相棒であるみよ子の答えはいつでも簡潔でありそして正しかった。
今現在においてもこの出力のままで航行していればいずれ原子炉エンジンに支障をきたす事は誰が見ても明らかだ。
船内がガタガタと大きく振動していた。船内温度も急激に上昇していた。
「ちっ」。カズキは拳を強く握りしめウィンドウスクリーンに映るスペースシップを睨みみよ子に告げた。
「出力を120%にダウン」
正体不明のスペースシップはゴールデン・ベアー号との距離をみるみる間に詰めてきた。
しかし射程距離に入ってもミサイルもビーム砲も撃ってはこなかった。恐らく弾切れなのだろう。あれだけ盛大な攻撃を仕掛けたのならば当然の事ではある。
それはこちらにも言えた事だ。ゴールデン・ベアー号も弾切れだった。盛大な攻撃を仕掛けられたならば盛大にやり返す。それがカズキの流儀だ。
今回はどちらの攻撃も相手に致命傷を与えるには至らなかった。しかし不意打ちを喰らった分のゴールデン・ベアー号の損害は大きかった。それが正体不明のスペースシップを振り切れなかった理由でもある。
一撃必中の攻撃が失敗したにも拘らず尚も追跡を止めようとしないスペースシップの意図する所は何なのか。
カズキは理解していた。
それはみよ子も同じだった。「こりゃあ本気で体当たりする気じゃ」
「・・・ああ」カズキは静かに頷いた。
「出力を80%にダウン」カズキはみよ子に告げた。
「なんじゃとぉっ!?」みよ子は驚いた。後8,000kmほどでアステロイドベルトの存在が確認されていた。そこに逃げ込めばスペースシップを振り切ることが出来る。カズキはそれを目指すものだと思っていた。
みよ子はカズキの顔を覗き込んだ。
カズキの表情には先ほどの焦りの色は見えなかった。落ち着いている。むしろ微かに笑っているようにも思えた。
この表情の時のカズキは信頼に値する。みよ子はそう思っていた。確かにアステロイドベルトまでは遠過ぎた。
「出力80%」みよ子は従った。
スペースシップがあっという間に間合いを詰める。その距離100km。
60・・・
40・・・
20・・・
「1号エンジンをパージする!」カズキの声が静まり返った船内に響いた。
「なっ、なん・・・」みよ子が驚く前にカズキが強化プラスチックカバーを叩き割り、中にある赤いレバーを力強く引いた。
稼働中のエンジンをパージする事など前代未聞である。パージした瞬間に爆発を起こしてもなんの不思議もない。
出力を低下させたことによって一時的に冷却された1号エンジンは爆発することなく射出された。それに伴いゴールデン・ベアー号のスピードも急激に落ちた。
「みよ子、出力全開!急げっ!」
「なっ、なんじゃあっ!!」みよ子は残りのエンジンを全開にした。
猛スピードで突っ込んできたスペースシップにこの近距離で突如現れた障害物を避ける事は不可能だった。スペースシップの鼻面にゴールデン・ベアー号の1号エンジンがのめり込む。
船内を粉々に破壊しながら尚も1号エンジンは止まる気配すらなかった。それはあたかもスペースシップのエンジンルームを目指しているがごとく破壊の限りを尽くして突き進む。
暫くの間、宇宙にはいつもの静寂が訪れていた。しかし船体内部から幾条もの光線をほとばしらせた後大爆発を起こしたスペースシップがその静寂を打ち消す。
爆発はゴールデン・ベアー号も巻き込んだが、残り2基のエンジンを250%の出力でその場を緊急離脱し被害を最小限にとどめた。
爆発のまばゆい明かりはとても美しかった。そしてその明かりを全身に受けた黄金の機体ゴールデン・ベアー号は漆黒の宇宙の暗闇の中一際光り輝いていた。
カズキ ~栄光の架橋~ [カズキ]
「そんなこと言ったって仕方ないじゃないか。」
カズキはまたその言葉を呟いた。
いつの頃からかその言葉を呟く事で自分の中にある不満やわだかまりを解決させていた。
ドラマで共演したベテラン女優のお小言。バラエティ番組での中堅芸人からの妬み。
それらを神妙な面持ちや偽りの笑顔でやり過ごした後で一人になった時に呟くのだった。
「そんなこと言ったって仕方ないじゃないか。」
しかしその言葉で不満やわだかまりが解決されていたわけではなかった。
大きな黒い塊が砕かれ、ただ細かい塵となっていただけだった。
呟くたびに細かな黒い塵がはらはらとカズキの心に降り注いだ。
それらはカズキの心の奥底へと沈み込み澱のように溜まっていくのだった。
今日もまたカズキは呟いた。
「そんなこと言ったって仕方ないじゃないか。」
「そんなこと言ったって仕方ないじゃないか!」
「そんなこと言ったって仕方ないじゃないかっ!」
カズキの心のまだ残っていた清らかな所に黒い塵が降り注がれ、
そうしてカズキの心は真っ黒になった。
カズキは荒れた。
荒れ果てたカズキの心はテレビの画面からも伝わってきた。口元だけは無理矢理に笑顔を装ってみても目はそうはいかなかった。目の奥にあるどす黒く淀みながらも不気味にメラメラと燃え上がる苛立ち。それをテレビカメラは捉えていた。
視聴者からの苦情の電話があったことを告げるプロデューサーに対してカズキは初めて面と向かって言った。
「そんなこと言ったって仕方ないじゃないかっ!」
自宅に帰りカズキはご自慢のアーノルド・パーマーのポロシャツコレクションすべてを引きちぎり、愛用の無線機を愛用のゴルフクラブで叩き壊した。
「こんなものどうなったっていいじゃないかっ!」
近くのコンビニでは、
「ポンタカードなんか持ってるわけないじゃないかっ!」
道を聞かれれば、
「2つ目の信号を右に曲がって線路沿いに行けば左側にあるじゃないかっ!郵便局がっ!」
カズキは荒れていた。
カズキは飲めなかった酒を飲むようになっていた。ボロボロにちぎれたポロシャツとズタズタに壊れた無線機。グシャグシャに折れ曲がったゴルフクラブが散在する薄暗い静かな部屋で浴びるようにロゼワインを飲み続けた。
何よりもロゼだった。赤よりも白よりも。
たまには赤でも。と浮気をしたが結局ロゼに戻るのだった。
いつもの様に今日もまたカズキはロゼを飲んでいた。実際には口に液体が入り喉を通過する。そしていつものロゼの味が残る。その事だけで自分は大好きなロゼを飲んでいるという事を理解している状態だった。
しかしいつもと違うのはその場所は薄暗くなかった。そして何故か複数の人間がいて、しかもそのうちの二人がゆずの『栄光の架橋』を熱唱していた。
頭が混乱し判然としない状態の中でカズキは隣に別の誰かが座っている事に気付いた。
カズキの方に向かって何かを話しかけているようだった。薄っすらとは聞こえるが『栄光の架橋』がサビに入っていてよく聞こえない。
顔を見ると女性のようだった。
更に向こうは話しかけているようだったが『栄光の架橋』でよく聞こえない。しかし何かがおかしい。
何がどうおかしいのか初めは分からなかったが不意に気付いた。
女性の口が全く動いていないのだ。
『栄光の架橋』は熱唱の甲斐無く54点だった。
「あんたぁ、それ何飲んどるん?」
女性は何故か目を細めてドスを利かせた声でカズキに質問をしてきた。今度はちゃんと口を動かしていた。
改めてよく見てみると女性は角刈りだった。まるで往年のやくざ映画の主人公のような。
ロゼワインを飲んでいる事を告げると女性は豪快に笑った。不思議な事に女性のお腹からも笑い声が聞こえてくるようだった。
(「そんなこと言ったって仕方ないじゃないか。」)
カズキは心の中でそう思ったが、女性のあまりにも気持ちのいい笑い方にその言葉を口にする事をしなかった。しまいには自分がピンク色の液体を手にしていること自体が面白くなり一緒に笑った。
笑い続ける女性にカズキは笑いながら言った。
「そんなこと言ったって仕方ないじゃないか。」
更に女性は笑いカズキも笑った。
『栄光の架橋』のイントロが聞こえてきた。先ほどの二人が再チャレンジをするようだ。
カズキはまたその言葉を呟いた。
いつの頃からかその言葉を呟く事で自分の中にある不満やわだかまりを解決させていた。
ドラマで共演したベテラン女優のお小言。バラエティ番組での中堅芸人からの妬み。
それらを神妙な面持ちや偽りの笑顔でやり過ごした後で一人になった時に呟くのだった。
「そんなこと言ったって仕方ないじゃないか。」
しかしその言葉で不満やわだかまりが解決されていたわけではなかった。
大きな黒い塊が砕かれ、ただ細かい塵となっていただけだった。
呟くたびに細かな黒い塵がはらはらとカズキの心に降り注いだ。
それらはカズキの心の奥底へと沈み込み澱のように溜まっていくのだった。
今日もまたカズキは呟いた。
「そんなこと言ったって仕方ないじゃないか。」
「そんなこと言ったって仕方ないじゃないか!」
「そんなこと言ったって仕方ないじゃないかっ!」
カズキの心のまだ残っていた清らかな所に黒い塵が降り注がれ、
そうしてカズキの心は真っ黒になった。
カズキは荒れた。
荒れ果てたカズキの心はテレビの画面からも伝わってきた。口元だけは無理矢理に笑顔を装ってみても目はそうはいかなかった。目の奥にあるどす黒く淀みながらも不気味にメラメラと燃え上がる苛立ち。それをテレビカメラは捉えていた。
視聴者からの苦情の電話があったことを告げるプロデューサーに対してカズキは初めて面と向かって言った。
「そんなこと言ったって仕方ないじゃないかっ!」
自宅に帰りカズキはご自慢のアーノルド・パーマーのポロシャツコレクションすべてを引きちぎり、愛用の無線機を愛用のゴルフクラブで叩き壊した。
「こんなものどうなったっていいじゃないかっ!」
近くのコンビニでは、
「ポンタカードなんか持ってるわけないじゃないかっ!」
道を聞かれれば、
「2つ目の信号を右に曲がって線路沿いに行けば左側にあるじゃないかっ!郵便局がっ!」
カズキは荒れていた。
カズキは飲めなかった酒を飲むようになっていた。ボロボロにちぎれたポロシャツとズタズタに壊れた無線機。グシャグシャに折れ曲がったゴルフクラブが散在する薄暗い静かな部屋で浴びるようにロゼワインを飲み続けた。
何よりもロゼだった。赤よりも白よりも。
たまには赤でも。と浮気をしたが結局ロゼに戻るのだった。
いつもの様に今日もまたカズキはロゼを飲んでいた。実際には口に液体が入り喉を通過する。そしていつものロゼの味が残る。その事だけで自分は大好きなロゼを飲んでいるという事を理解している状態だった。
しかしいつもと違うのはその場所は薄暗くなかった。そして何故か複数の人間がいて、しかもそのうちの二人がゆずの『栄光の架橋』を熱唱していた。
頭が混乱し判然としない状態の中でカズキは隣に別の誰かが座っている事に気付いた。
カズキの方に向かって何かを話しかけているようだった。薄っすらとは聞こえるが『栄光の架橋』がサビに入っていてよく聞こえない。
顔を見ると女性のようだった。
更に向こうは話しかけているようだったが『栄光の架橋』でよく聞こえない。しかし何かがおかしい。
何がどうおかしいのか初めは分からなかったが不意に気付いた。
女性の口が全く動いていないのだ。
『栄光の架橋』は熱唱の甲斐無く54点だった。
「あんたぁ、それ何飲んどるん?」
女性は何故か目を細めてドスを利かせた声でカズキに質問をしてきた。今度はちゃんと口を動かしていた。
改めてよく見てみると女性は角刈りだった。まるで往年のやくざ映画の主人公のような。
ロゼワインを飲んでいる事を告げると女性は豪快に笑った。不思議な事に女性のお腹からも笑い声が聞こえてくるようだった。
(「そんなこと言ったって仕方ないじゃないか。」)
カズキは心の中でそう思ったが、女性のあまりにも気持ちのいい笑い方にその言葉を口にする事をしなかった。しまいには自分がピンク色の液体を手にしていること自体が面白くなり一緒に笑った。
笑い続ける女性にカズキは笑いながら言った。
「そんなこと言ったって仕方ないじゃないか。」
更に女性は笑いカズキも笑った。
『栄光の架橋』のイントロが聞こえてきた。先ほどの二人が再チャレンジをするようだ。
今日子 [カズキ]
崖の上に立つ一軒家にみよ子は向かっていた。あの切腹(未遂)から15年が過ぎていた。
切腹(未遂)の傷跡は消える事は無かった。むしろみよ子自身の成長に合わせるように傷跡もまるで成長しているようだった。
学生時代の部活の着替えの際に友人から「あんたの盲腸左なの?」と問われれば、「いやぁ、こりゃあ腹切りの際のもんじゃけぇ。ゆうたら不肖の傷跡。っちゅうところになるんかのぉ。ワッハッハッ!」と、照れ隠しに『仁義なき戦い』の文太兄いの物真似で正直に答えてみても誰も信じる者はいなかった。
その傷口が1か月ほど前に突然喋り出した時には、友人たちの間では豪放磊落の名をほしいままにしていたみよ子でさえ度肝を抜かれた。
それは腹話術を練習していた時の事だった。
みよ子の腹話術は人形のキョーコを汚い言葉で責め立てる超ドS腹話術である。
その公序良俗を激しく欠くネタに多くの者をドン引きさせるものの、一部にカルト的な支持を受け「アンダーグラウンド芸の極致!」と言わしめた。
みよ子は何かに抗っていた。世間なのか社会なのかそれとも自分自身なのか。とにかく世の中の奇麗なものを否定して拒否してぶっ壊してやりたかった。
練習に熱が入り、鬼の形相、身の毛もよだつ汚辱ワードでキョーコを責め立てていた時だった。
「モウヤメテ」と、みよ子のお腹から声が聞こえた。
切なる願い「モウヤメテ」。それが今日子が発した初めての言葉であった。
その崖の上の一軒家の主は医者であった。診察をしてもらった大学病院の医師の紹介だった。何しろその症例を見た事のある医学関係者はその男ただ一人しかいないのだ。
男は高額な報酬を要求する事で半ば医学界からは追放されているとの事だった。要はもぐりの医者だ。
ところで一軒家までの道中、つぎはぎだらけのヒョウタンみたいな物体を見かけたが、あれはなんだったのだろう?みよ子は何か別の世界に入り込んでしまったような気がした。
一軒家に着くとまるでお人形のような小さな女の子が玄関前でこちらを見ていた。みよ子の顔を見るなり頬に両手をあて奇声を発するとどこかへ行ってしまった。「あっちょおぷりけい」とは一体何を意味する言葉なのだろう?皆目見当がつかなかった。
また、つぎはぎのヒョウタンが見えた。呆然と立ち尽くすみよ子の前に全身黒づくめの男が玄関から顔を出し、ぶっきらぼうに「ほぉう、あんたですかい」とみよ子を一瞥して言った。
男はドバイで緊急のオペがあるという事で早速診察をしてもらった。
お腹の傷口には目の筋のようなもの、鼻の筋のようなもの、そして輪郭のようなものが出来つつあった。それは人間の顔と言ってほぼよかった。
男は「ふうむ」と言いながら立ち上がると、開け放していた窓から部屋の中に入ってきた風によってマントがヒラリとめくれ上がり、マントの内側に忍ばせていた手術用のメスがキラリと光った。
その瞬間傷口の目と思われる部分が見開かれ、男に激痛が走った。男は苦痛に顔を歪め手で頭を抑え天を仰いだ。
先ほどの少女がみよ子と男の間に入り、みよ子の傷口をじっと見つめ何かを念じるような顔つきから次第に表情が柔らかくなると男の苦痛も消え去っていた。
男の診断ではそれは確かに人面瘡であるとの事だった。しかし以前見たものとは違うものらしく。いわば良性の人面瘡ではないかという事だった。
そして人間の体には人間の理解を超えた事が起こることを人形のような小さな少女の身の上話で教えてくれた。
男は最後に「ひょっとするとこいつぁあんたを守ってくれているのかもしれませんぜ。」と付け加えた。
そう、確かに今日子はそれ以降ずっとみよ子を守ってくれた。みよ子だけではなく人類をも。人類が忘れてはならない数々の出来事。
突如日本海海上に隆起した巨大海底火山の噴火をたった一人でせき止めた今日子。
某国が開発し暴走した巨大生物との死闘を戦い抜き勝利した今日子。
宇宙からやってきた侵略者軍団にヒョウタン軍団を引き連れ立ち向かっていった今日子。
それらはすべてみよ子を守るためだった。
そして今現在も今日子はみよ子を守るため、世界中で爆発的に猛威を振るおうとしている新型ウィルスと戦っている。
頑張れ今日子!負けるな今日子!
みよ子が一軒家を出る際みんなが送ってくれた。
今回の診察料はドバイの大金持ちに上乗せするとの事だった。「なあに、有る所には有るもんですぜ。お嬢さん。」と男はニヤリと笑った。
女の子はまた奇声を発した。「あちょぉーぶりてん」とはなんなのだろう?イギリスと何か関係があるのだろうか。
つぎはぎのヒョウタンはその数を大幅に増やし至る所にいた。もう気にするのが馬鹿らしくなっていた。
さっきまでは見かけなかった海パン姿に赤いブーツの男の子、もじゃもじゃ頭に鼻の大きなおじいさん、金色に輝く鳥や白いライオンまでいた。
その中央にはベレー帽にメガネをかけたおじさん。皆が笑顔でみよ子を送ってくれた。
みよ子の中にあった得体のしれないどす黒い何かが薄れようとしていた。今日子の言う通り超ドS腹話術はやめる事にした。
今日からは自分ひとりではなく今日子とふたりで生きてゆくのだ。
みよ子は清々しい気持ちでバイト先のカラオケスナックへと向かった。
みよ子の新しい一歩を祝福するように、夕暮れに赤く染まった空に無数のヒョウタンが高く高く舞い上がっていった。
切腹(未遂)の傷跡は消える事は無かった。むしろみよ子自身の成長に合わせるように傷跡もまるで成長しているようだった。
学生時代の部活の着替えの際に友人から「あんたの盲腸左なの?」と問われれば、「いやぁ、こりゃあ腹切りの際のもんじゃけぇ。ゆうたら不肖の傷跡。っちゅうところになるんかのぉ。ワッハッハッ!」と、照れ隠しに『仁義なき戦い』の文太兄いの物真似で正直に答えてみても誰も信じる者はいなかった。
その傷口が1か月ほど前に突然喋り出した時には、友人たちの間では豪放磊落の名をほしいままにしていたみよ子でさえ度肝を抜かれた。
それは腹話術を練習していた時の事だった。
みよ子の腹話術は人形のキョーコを汚い言葉で責め立てる超ドS腹話術である。
その公序良俗を激しく欠くネタに多くの者をドン引きさせるものの、一部にカルト的な支持を受け「アンダーグラウンド芸の極致!」と言わしめた。
みよ子は何かに抗っていた。世間なのか社会なのかそれとも自分自身なのか。とにかく世の中の奇麗なものを否定して拒否してぶっ壊してやりたかった。
練習に熱が入り、鬼の形相、身の毛もよだつ汚辱ワードでキョーコを責め立てていた時だった。
「モウヤメテ」と、みよ子のお腹から声が聞こえた。
切なる願い「モウヤメテ」。それが今日子が発した初めての言葉であった。
その崖の上の一軒家の主は医者であった。診察をしてもらった大学病院の医師の紹介だった。何しろその症例を見た事のある医学関係者はその男ただ一人しかいないのだ。
男は高額な報酬を要求する事で半ば医学界からは追放されているとの事だった。要はもぐりの医者だ。
ところで一軒家までの道中、つぎはぎだらけのヒョウタンみたいな物体を見かけたが、あれはなんだったのだろう?みよ子は何か別の世界に入り込んでしまったような気がした。
一軒家に着くとまるでお人形のような小さな女の子が玄関前でこちらを見ていた。みよ子の顔を見るなり頬に両手をあて奇声を発するとどこかへ行ってしまった。「あっちょおぷりけい」とは一体何を意味する言葉なのだろう?皆目見当がつかなかった。
また、つぎはぎのヒョウタンが見えた。呆然と立ち尽くすみよ子の前に全身黒づくめの男が玄関から顔を出し、ぶっきらぼうに「ほぉう、あんたですかい」とみよ子を一瞥して言った。
男はドバイで緊急のオペがあるという事で早速診察をしてもらった。
お腹の傷口には目の筋のようなもの、鼻の筋のようなもの、そして輪郭のようなものが出来つつあった。それは人間の顔と言ってほぼよかった。
男は「ふうむ」と言いながら立ち上がると、開け放していた窓から部屋の中に入ってきた風によってマントがヒラリとめくれ上がり、マントの内側に忍ばせていた手術用のメスがキラリと光った。
その瞬間傷口の目と思われる部分が見開かれ、男に激痛が走った。男は苦痛に顔を歪め手で頭を抑え天を仰いだ。
先ほどの少女がみよ子と男の間に入り、みよ子の傷口をじっと見つめ何かを念じるような顔つきから次第に表情が柔らかくなると男の苦痛も消え去っていた。
男の診断ではそれは確かに人面瘡であるとの事だった。しかし以前見たものとは違うものらしく。いわば良性の人面瘡ではないかという事だった。
そして人間の体には人間の理解を超えた事が起こることを人形のような小さな少女の身の上話で教えてくれた。
男は最後に「ひょっとするとこいつぁあんたを守ってくれているのかもしれませんぜ。」と付け加えた。
そう、確かに今日子はそれ以降ずっとみよ子を守ってくれた。みよ子だけではなく人類をも。人類が忘れてはならない数々の出来事。
突如日本海海上に隆起した巨大海底火山の噴火をたった一人でせき止めた今日子。
某国が開発し暴走した巨大生物との死闘を戦い抜き勝利した今日子。
宇宙からやってきた侵略者軍団にヒョウタン軍団を引き連れ立ち向かっていった今日子。
それらはすべてみよ子を守るためだった。
そして今現在も今日子はみよ子を守るため、世界中で爆発的に猛威を振るおうとしている新型ウィルスと戦っている。
頑張れ今日子!負けるな今日子!
みよ子が一軒家を出る際みんなが送ってくれた。
今回の診察料はドバイの大金持ちに上乗せするとの事だった。「なあに、有る所には有るもんですぜ。お嬢さん。」と男はニヤリと笑った。
女の子はまた奇声を発した。「あちょぉーぶりてん」とはなんなのだろう?イギリスと何か関係があるのだろうか。
つぎはぎのヒョウタンはその数を大幅に増やし至る所にいた。もう気にするのが馬鹿らしくなっていた。
さっきまでは見かけなかった海パン姿に赤いブーツの男の子、もじゃもじゃ頭に鼻の大きなおじいさん、金色に輝く鳥や白いライオンまでいた。
その中央にはベレー帽にメガネをかけたおじさん。皆が笑顔でみよ子を送ってくれた。
みよ子の中にあった得体のしれないどす黒い何かが薄れようとしていた。今日子の言う通り超ドS腹話術はやめる事にした。
今日からは自分ひとりではなく今日子とふたりで生きてゆくのだ。
みよ子は清々しい気持ちでバイト先のカラオケスナックへと向かった。
みよ子の新しい一歩を祝福するように、夕暮れに赤く染まった空に無数のヒョウタンが高く高く舞い上がっていった。
みよ子 [カズキ]
事の始まりはみよ子が小学1年生の時だった。
みよ子は祖父の事が大好きだった。となれば祖父の好きな時代劇も好きになるのが道理というもの。
ある日曜日の午後。家族はそれぞれの所用で出掛けていた。みよ子は何とはなしにチャンネルをガチャガチャ替えながらテレビを眺めていた。
時代劇をやっているチャンネルがあった。それはいつもと違い白黒であった。言葉遣いもやけに堅苦しい。それでもみよ子は最後にはみんな揃って「よよよい、よよよい、よよよい、よい」が見れるものだと思いその時代劇を見ていた。
しかしその時代劇は小学校低学年、あまつさえ成人男子でさえもハードルの高い超リアル指向の時代劇であった。
理不尽な申し付けによって切腹せざるを得なくなった武士。必死の形相で腹を真一文字にかっ斬る武士を白黒の画面が克明に捉え、未熟な介錯人による介錯で何度も斬りつけられる度にグシャッ、グシャッという生々しい音と、武士の何とも形容しがたい呻き声が流れる。そのリアル過ぎる表現。
そして切腹後の介錯人に飛び散った血しぶきと見届け人の蒼白となった顔面。白黒ながらその見事なコントラスト。
演出と映像によって見る者に迫ってくる無常感にみよ子は心酔した。
みよ子の中で切腹ブームが来た。ランドセルを背負いながらも心の中では常に白装束であった。
しかし小学1年生に刃物はなかなか持たせてもらえなかった。常々機会を窺っていたがそのチャンスはやってきた。工作の時間に使用する事になったボンナイフである。
「これを手に入れられれば、あたいもせっぷくができる!」みよ子の目は輝いた。
しかし工作の時間が終わればボンナイフは返却しなければならなかった。「どうするみよ子、どうする」みよ子は必死に考えた。
みよ子の気付かない間に工作の時間は終わり給食の時間になっていた。
手にはボンナイフが握られていたままだった。周囲を見渡しそーっとポケットにしまうみよ子であった。
その夜、みよ子切腹の時は遂にやってきた。
まずは練習である。世の小学1年生は無謀な一発勝負を挑み玉砕しがち。クラスメイトを観察してみよ子が得た教訓だ。
ボンナイフを腹にあててみる。ひんやりと冷たい。軽くスッと動かしてみる。
めちゃめちゃ痛かった。
思えばみよ子は痛みに弱い子だった。予防接種の時などは人一倍騒ぐ子だった。
ボンナイフを机の引き出しにそっとしまい「あたい、お侍さんじゃなくてよかったわ。」と独り言を呟くみよ子の中の切腹ブームはこれにて終了した。
おへその横に1センチほどの傷跡を残して。
みよ子は祖父の事が大好きだった。となれば祖父の好きな時代劇も好きになるのが道理というもの。
ある日曜日の午後。家族はそれぞれの所用で出掛けていた。みよ子は何とはなしにチャンネルをガチャガチャ替えながらテレビを眺めていた。
時代劇をやっているチャンネルがあった。それはいつもと違い白黒であった。言葉遣いもやけに堅苦しい。それでもみよ子は最後にはみんな揃って「よよよい、よよよい、よよよい、よい」が見れるものだと思いその時代劇を見ていた。
しかしその時代劇は小学校低学年、あまつさえ成人男子でさえもハードルの高い超リアル指向の時代劇であった。
理不尽な申し付けによって切腹せざるを得なくなった武士。必死の形相で腹を真一文字にかっ斬る武士を白黒の画面が克明に捉え、未熟な介錯人による介錯で何度も斬りつけられる度にグシャッ、グシャッという生々しい音と、武士の何とも形容しがたい呻き声が流れる。そのリアル過ぎる表現。
そして切腹後の介錯人に飛び散った血しぶきと見届け人の蒼白となった顔面。白黒ながらその見事なコントラスト。
演出と映像によって見る者に迫ってくる無常感にみよ子は心酔した。
みよ子の中で切腹ブームが来た。ランドセルを背負いながらも心の中では常に白装束であった。
しかし小学1年生に刃物はなかなか持たせてもらえなかった。常々機会を窺っていたがそのチャンスはやってきた。工作の時間に使用する事になったボンナイフである。
「これを手に入れられれば、あたいもせっぷくができる!」みよ子の目は輝いた。
しかし工作の時間が終わればボンナイフは返却しなければならなかった。「どうするみよ子、どうする」みよ子は必死に考えた。
みよ子の気付かない間に工作の時間は終わり給食の時間になっていた。
手にはボンナイフが握られていたままだった。周囲を見渡しそーっとポケットにしまうみよ子であった。
その夜、みよ子切腹の時は遂にやってきた。
まずは練習である。世の小学1年生は無謀な一発勝負を挑み玉砕しがち。クラスメイトを観察してみよ子が得た教訓だ。
ボンナイフを腹にあててみる。ひんやりと冷たい。軽くスッと動かしてみる。
めちゃめちゃ痛かった。
思えばみよ子は痛みに弱い子だった。予防接種の時などは人一倍騒ぐ子だった。
ボンナイフを机の引き出しにそっとしまい「あたい、お侍さんじゃなくてよかったわ。」と独り言を呟くみよ子の中の切腹ブームはこれにて終了した。
おへその横に1センチほどの傷跡を残して。
カズキ・リターン [カズキ]
限界だった。いや、限界はとうに過ぎていた。
それはアーユルヴェーダにおけるネトラバスティに近い状態と言っても過言ではないだろう。1ミリでも体を動かせば涙がこぼれ落ちる事は確実だった。
しかしそれ以前に首が限界だった。肩も腰も太ももも、膝も脛も踵まで。
何せ小一時間は天井を見つめ続けていたのだから。
とうに過ぎた限界をさらに超え遂には膝から崩れ落ちたが、決して天井からは目を離さなかった。
衝撃で涙がキラキラと宙に舞いこぼれ落ちた。
そうしてカズキは泣いた。ワァンワァンと声を上げて。
泣いた。泣いて泣いて泣き続けた。
涙が枯れ果てるまで泣いたその後にやってきたのは清々しさではなく虚無だった。
カズキの周囲にまとわりつく暗闇はさらに色濃さを増し、もう太陽の光さえ届かないほどの深宇宙の暗闇だった。
カズキの中に入り込んだ虚無がその暗闇と溶け合い、自分はこのまま消えてしまうのではないかと思えた。
その時目の前に浮かんだのはあの子の笑顔だった。
あの子に出会った頃のカズキは荒れていた。
仕事、家族、人間関係、あれほどまでに情熱を傾けていたゴルフまで。全てがどうでもよくなっていた。
ストイックなまでに禁じていた酒と女とギャンブルに手を出し自堕落に毎日をやり過ごしていた。
そんな時に出会ったのがカラオケスナックで働くみよ子ちゃんだった。
決して美人とは言えないが屈託のない笑顔に荒れ果てた心が癒されてゆくのをカズキは感じ取っていた。
みよ子ちゃんの笑顔の裏側に隠された秘密には気付かぬまま。
みよ子ちゃんの特技は腹話術だった。それは見事な腹話術だった。
カズキはことのほか感心し、「テレビ局のプロデューサーを紹介するからテレビに出てみなよ。」と軽口を叩いたが、みよ子ちゃんはその事には乗り気ではなかった。
自分が芸能界でそれなりの地位にいる事をアピールしたいカズキはスナックに行く度にその事を口にしたが、みよ子ちゃんはいつも笑顔ではぐらかすのだった。
ある日本当にプロデューサーを連れてきたカズキにみよ子ちゃんはいつもの笑顔ではなく困った顔を見せ、カズキにだけ真相を打ち明けるのだった。
みよ子ちゃんは重い病を抱えていた。
人面瘡と言う奇病であった。傷口に人面が現れやがてその人面が意思を持つという病である。
みよ子ちゃんのおへその左側にあったそれは本当に人間の顔だった。目を開ける事は出来なかったがそれが幼な子の寝顔のように思えた。
カズキが「こんにちは」と呼び掛けると少し恥ずかしげに「コンニチハ」と可愛らしい声で応えるのだった。
みよ子ちゃんはその子の事を今日子と呼びとても愛おしんでいた。
「だって、今日子は一生懸命生きようとしてるんだもん。」と、涙ぐみながらいつもの笑顔を見せるのだった。
みよ子ちゃんと今日子ちゃんに生きてゆく気力を分けてもらったカズキだったが、仕事への情熱は戻らないままだった。
一時とは言え酒と女とギャンブルに溺れた自分が癒しの存在などと他人様に思われる事がどうしても許せず、週末の行楽地の天気の予想にも身が入らないのだった。
そんな時に出会ったのがあの歌だった。
そのレコーディングにも最初は乗り気ではなかったのだが、何度も歌っているうちに心が軽くなってゆく気がした。
カズキの暗闇は続いていた。
太陽の輝きも星々の煌めきもまるで存在しない暗闇。その暗闇に溶けてゆく自分。
みよ子ちゃんの笑顔も今はもう薄っすらとしか思い出せない。
そんな時にあの歌のメロディがぼんやりと浮かんできた。
必死にメロディを思い出し声にならない声で口ずさむと一瞬目の前で何かが光った様な気がした。
何度も何度も口ずさみ次第に声がはっきりと出るようになると、光も次第に大きく明るくなっていった。
何度も何度も口ずさみ、
そしてカズキは光に包まれた。
カズキはあの見慣れたリビングの天井を見つめていた。
夫婦喧嘩はまだ続いている。完全無視もされたままだ。
だがもうそんな事はどうでもよかった。今はただ、みよ子ちゃんと今日子ちゃんに会いたかった。
外に出ると陽の光がとても眩しかった。
カズキはカラオケスナックへと向かって歩き出した。
あの歌を口ずさみながら。
それはアーユルヴェーダにおけるネトラバスティに近い状態と言っても過言ではないだろう。1ミリでも体を動かせば涙がこぼれ落ちる事は確実だった。
しかしそれ以前に首が限界だった。肩も腰も太ももも、膝も脛も踵まで。
何せ小一時間は天井を見つめ続けていたのだから。
とうに過ぎた限界をさらに超え遂には膝から崩れ落ちたが、決して天井からは目を離さなかった。
衝撃で涙がキラキラと宙に舞いこぼれ落ちた。
そうしてカズキは泣いた。ワァンワァンと声を上げて。
泣いた。泣いて泣いて泣き続けた。
涙が枯れ果てるまで泣いたその後にやってきたのは清々しさではなく虚無だった。
カズキの周囲にまとわりつく暗闇はさらに色濃さを増し、もう太陽の光さえ届かないほどの深宇宙の暗闇だった。
カズキの中に入り込んだ虚無がその暗闇と溶け合い、自分はこのまま消えてしまうのではないかと思えた。
その時目の前に浮かんだのはあの子の笑顔だった。
あの子に出会った頃のカズキは荒れていた。
仕事、家族、人間関係、あれほどまでに情熱を傾けていたゴルフまで。全てがどうでもよくなっていた。
ストイックなまでに禁じていた酒と女とギャンブルに手を出し自堕落に毎日をやり過ごしていた。
そんな時に出会ったのがカラオケスナックで働くみよ子ちゃんだった。
決して美人とは言えないが屈託のない笑顔に荒れ果てた心が癒されてゆくのをカズキは感じ取っていた。
みよ子ちゃんの笑顔の裏側に隠された秘密には気付かぬまま。
みよ子ちゃんの特技は腹話術だった。それは見事な腹話術だった。
カズキはことのほか感心し、「テレビ局のプロデューサーを紹介するからテレビに出てみなよ。」と軽口を叩いたが、みよ子ちゃんはその事には乗り気ではなかった。
自分が芸能界でそれなりの地位にいる事をアピールしたいカズキはスナックに行く度にその事を口にしたが、みよ子ちゃんはいつも笑顔ではぐらかすのだった。
ある日本当にプロデューサーを連れてきたカズキにみよ子ちゃんはいつもの笑顔ではなく困った顔を見せ、カズキにだけ真相を打ち明けるのだった。
みよ子ちゃんは重い病を抱えていた。
人面瘡と言う奇病であった。傷口に人面が現れやがてその人面が意思を持つという病である。
みよ子ちゃんのおへその左側にあったそれは本当に人間の顔だった。目を開ける事は出来なかったがそれが幼な子の寝顔のように思えた。
カズキが「こんにちは」と呼び掛けると少し恥ずかしげに「コンニチハ」と可愛らしい声で応えるのだった。
みよ子ちゃんはその子の事を今日子と呼びとても愛おしんでいた。
「だって、今日子は一生懸命生きようとしてるんだもん。」と、涙ぐみながらいつもの笑顔を見せるのだった。
みよ子ちゃんと今日子ちゃんに生きてゆく気力を分けてもらったカズキだったが、仕事への情熱は戻らないままだった。
一時とは言え酒と女とギャンブルに溺れた自分が癒しの存在などと他人様に思われる事がどうしても許せず、週末の行楽地の天気の予想にも身が入らないのだった。
そんな時に出会ったのがあの歌だった。
そのレコーディングにも最初は乗り気ではなかったのだが、何度も歌っているうちに心が軽くなってゆく気がした。
カズキの暗闇は続いていた。
太陽の輝きも星々の煌めきもまるで存在しない暗闇。その暗闇に溶けてゆく自分。
みよ子ちゃんの笑顔も今はもう薄っすらとしか思い出せない。
そんな時にあの歌のメロディがぼんやりと浮かんできた。
必死にメロディを思い出し声にならない声で口ずさむと一瞬目の前で何かが光った様な気がした。
何度も何度も口ずさみ次第に声がはっきりと出るようになると、光も次第に大きく明るくなっていった。
何度も何度も口ずさみ、
そしてカズキは光に包まれた。
カズキはあの見慣れたリビングの天井を見つめていた。
夫婦喧嘩はまだ続いている。完全無視もされたままだ。
だがもうそんな事はどうでもよかった。今はただ、みよ子ちゃんと今日子ちゃんに会いたかった。
外に出ると陽の光がとても眩しかった。
カズキはカラオケスナックへと向かって歩き出した。
あの歌を口ずさみながら。
カズキ [カズキ]
ショックだった。いや屈辱だった。
生まれてから今まで年上世代たちからの受けは抜群にいいはずだった。
そしてその事を最大の武器として芸能界という世界でこれまで活躍していたエナリカズキという存在。
例え夫婦喧嘩の真っ最中というアドバンテージは有るにしても完全無視は有り得なかった。いや有ってはならなかった。
これまでに無視された事など無いと言えばそれは嘘になるだろう。学生時代のクラスメイトからの妬み嫉みなどは日常茶飯事と言っても差し支えは無い。
しかし、こと年上世代とあれば話は全くの別だ。とにかく受けが抜群に良かった。自分たちの子供と比較して現代風ではない朴訥な雰囲気に心癒される部分が少なからず有るのであろう。
とにもかくにも受けが抜群に良かった。
そんな自分へのまさかの完全無視。呆然とした。まるで宇宙の暗闇が自分だけに襲いかかってきたかのように目の前が真っ暗になった。
そして鼻の奥がツンとなり、ただただ涙が溢れてきた。
しかし涙を流さなかった。それだけが今唯一出来るエナリカズキとしての意地だった。
これまでで最高に受けが抜群に良かったあの日、あの時の、あの場所での事。それだけを脳裏に思い浮かべ、ひたすらに天井を見つめ続けた。
涙がこぼれ落ちない様に。
生まれてから今まで年上世代たちからの受けは抜群にいいはずだった。
そしてその事を最大の武器として芸能界という世界でこれまで活躍していたエナリカズキという存在。
例え夫婦喧嘩の真っ最中というアドバンテージは有るにしても完全無視は有り得なかった。いや有ってはならなかった。
これまでに無視された事など無いと言えばそれは嘘になるだろう。学生時代のクラスメイトからの妬み嫉みなどは日常茶飯事と言っても差し支えは無い。
しかし、こと年上世代とあれば話は全くの別だ。とにかく受けが抜群に良かった。自分たちの子供と比較して現代風ではない朴訥な雰囲気に心癒される部分が少なからず有るのであろう。
とにもかくにも受けが抜群に良かった。
そんな自分へのまさかの完全無視。呆然とした。まるで宇宙の暗闇が自分だけに襲いかかってきたかのように目の前が真っ暗になった。
そして鼻の奥がツンとなり、ただただ涙が溢れてきた。
しかし涙を流さなかった。それだけが今唯一出来るエナリカズキとしての意地だった。
これまでで最高に受けが抜群に良かったあの日、あの時の、あの場所での事。それだけを脳裏に思い浮かべ、ひたすらに天井を見つめ続けた。
涙がこぼれ落ちない様に。
アヲハタブルーネヴァーベリーエンディングジャムストーリー [カズキ]
最近映画館では「キューピーハーフゥ」からアヲハタブルーベリージャムのCMに切り替わりましたが。
http://www.kewpie.co.jp/know/cm/jamhistory/2012/2012_01.html
あのCMの軽い引っ掛けに何かもやぁんとした気分になるんだな。
と、母は言った。
と、父は言った。
あら、そんなこと言ってないじゃない。と、母は言った。
あの時君は確かにそう言ったよ。と、父は言った。
いいえ言ってなんかいないわ。と、母は言った。
あなたはいつもそうよ、勝手に決めつけて。とも、母は言った。
あの時のあの事だってそうじゃない。と、母は新たな展開を打ち出した。
おいおい、それは君だって納得しての事じゃないか。と、父は抵抗を試みた。
それは私が納得しているとあなたが思い込みたいだけなのよ。と、母はバッサリと切り捨てた。
そんなこと言ったって仕方ないじゃないか。と、エナリカズキがしゃしゃり出た。が無視された。
なんで君はいつもあの時の事を持ち出すんだよ。と、父は言った。
それはあの時ブルーベリージャムを初めて買ったからなんだな。
と、母は言った。
と、父は・・・
http://www.kewpie.co.jp/know/cm/jamhistory/2012/2012_01.html
あのCMの軽い引っ掛けに何かもやぁんとした気分になるんだな。
と、母は言った。
と、父は言った。
あら、そんなこと言ってないじゃない。と、母は言った。
あの時君は確かにそう言ったよ。と、父は言った。
いいえ言ってなんかいないわ。と、母は言った。
あなたはいつもそうよ、勝手に決めつけて。とも、母は言った。
あの時のあの事だってそうじゃない。と、母は新たな展開を打ち出した。
おいおい、それは君だって納得しての事じゃないか。と、父は抵抗を試みた。
それは私が納得しているとあなたが思い込みたいだけなのよ。と、母はバッサリと切り捨てた。
そんなこと言ったって仕方ないじゃないか。と、エナリカズキがしゃしゃり出た。が無視された。
なんで君はいつもあの時の事を持ち出すんだよ。と、父は言った。
それはあの時ブルーベリージャムを初めて買ったからなんだな。
と、母は言った。
と、父は・・・





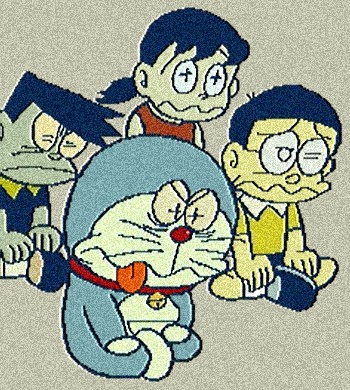








-1.jpg)
.jpg)


